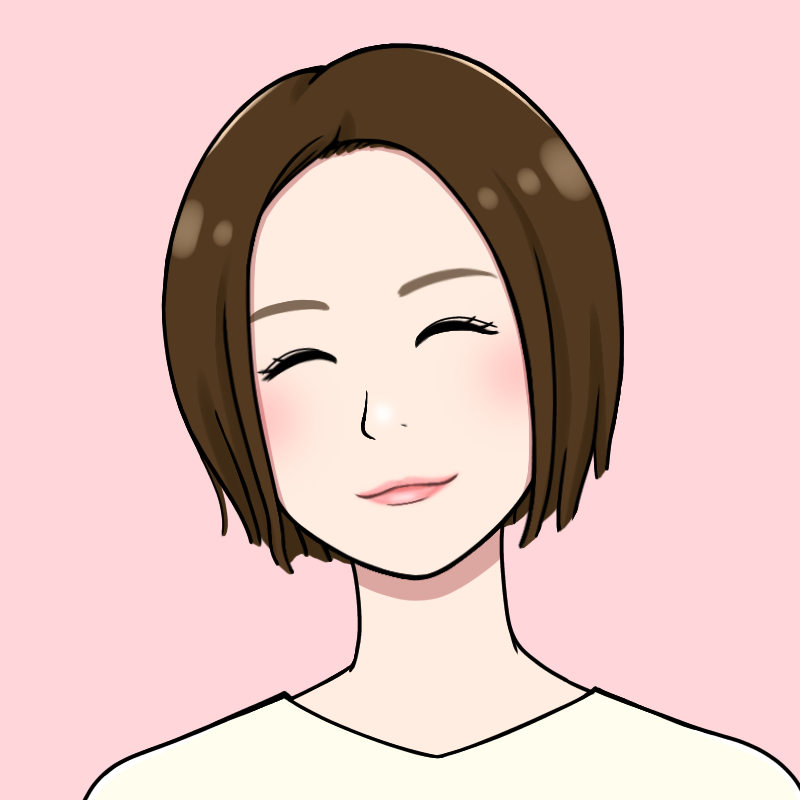HSCの中には、いわゆる「育てにくい」と感じる子も少なくないそうです。
明橋大二先生によると、HSCでHSS(刺激を求めるタイプ)の特性をもつ子や、
感情反応の強い子が、育てにくいと感じることが多いそうです。
そのような育てにくいと感じる子には、どのように接すればいいのでしょうか。
明橋大二先生に、育てにくいと感じるHSCとの接し方について、
教えていただきましょう。
Contents
明橋大二先生はどんな人?明橋大二先生のプロフィール
明橋大二先生のことを初めて知った方もいらっしゃるかもしれませんので、明橋大二先生のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。
明橋 大二(あけはしだいじ)
昭和34年、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 子育てカウンセラー・心療内科医。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて、真生会富山病院心療内科部長。 児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。 専門は精神病理学、児童思春期精神医療。
著書は「なぜ生きる」(共著)、「輝ける子」、「思春期にがんばってる子」、「翼ひろげる子」、「この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ」、「10代からの子育てハッピーアドバイス」など多数。
明橋大二先生のおかげで子育てで大事なことが分かり、悩みが減って子育てが楽しくなりました。
明橋大二先生より、育てにくいと感じるHSCとの接し方
育てにくい子は、長い目で見れば、心配のない子です
かんしゃくは、その子が傷ついているサインかもしれません
HSC(ひといちばい敏感な子)というと、
慎重で、内向的で、引きこもりがち子と思われがちですが、
ほとんど真逆のタイプの子もいます。
そういう子の中には、いわゆる「育てにくい」と感じる子も少なくありません。
特に、HSCでHSS(刺激を求めるタイプ)の特性を持った子や、
感情反応の強い子は、育てにくいと感じることが多いようです。
行動的ではありますが、すぐに押しつぶされてしまい、
求めている平和が簡単に崩れます。
かんしゃくが激しく、文句が多いです。ささいなことで、大げさに騒ぎます。
あるいは、ちょっと注意しただけで、逆ギレする。うまくいかないと八つ当たりする。
被害妄想的に取る。過度に落ち込むのでフォローがたいへんなこともあります。
友達と遊んでいると、それほどではないことでも、ひどいことをされたと言って、
ささいなことで傷ついてしまいます。
実際に傷ついているし、それをうまく表現できないから、
親に八つ当たりするしかなくて、かんしゃくになっているだけなのですが、
時にはわがままとしか思えないこともあります。
あるいは、こんな自分が受け入れられるのか不安で、確かめたいから、
試し行動に出ているだけなのに、親にとっては、うんざりしてしまうこともあります。
親もだんだん疲れてきて、イライラしてきます。
ところがそういうこちらのイライラをいち早く察知するのがHSCなので、
それをさらに否定されたと思い込み、よけいに逆ギレすることもあります。
本当はひといちばい傷ついている、ひといちばい助けを求めているのに、
それをうまく表現できず、逆ギレしたり、意地を張ったりする、という形で出すので、
よけいに怒られてしまうのです。
しかし一方で、小さい子の面倒を見たり、家族のケンカを仲裁したり、
優しい面もあります。
傷つく原因を見てみましょう
では、このように、育てにくい子の場合は、どのように接すればいいでしょうか?
こういう子の場合、まず、表面的な行動ばかりに目を奪われずに、
「この子は、実は傷ついているのかもしれない」と考えてみることが必要です。
「自分の思いどおりにならない」「親に叱られた」
「人が言うことを聞いてくれなかった」「自分の思う結果が出なかった」
こういうこと一つ一つが、敏感な子にとっては、傷つく原因になります。
そこでかんしゃくを起こして、それを周囲から「わがまま」と取られて、
「ちょっとは言うことを聞きなさい!」「しかたないじゃないの!」と叱られて、
また傷つく、という悪循環になっています。
自分をコントロールできるようになれば大丈夫です
こういう子に必要なのは、自分をコントロールする力です。
しかし、後で自分が困るとわかっていても、反応を止められず、
感情的な行動をとって、周りから孤立してしまうのがまた、こういう子の特性です。
そこで大切なのは、自分をコントロールしてくれる親の存在です。
そのためには、まず親が、少し落ち着くことが必要です。
親がヒートアップしていると、子どももますます興奮してしまいます。
親が少し離れて一呼吸おく。疲れたときは、他の大人にしばらく変わってもらう。
親が少し落ち着いたら、子どもも徐々に落ち着いてきます。
そこで、「どうしたの」とか、「嫌だったんだね」と気持ちを聞きます。
そのうえで、「そういうときは、言葉で言えばいいんだよ」とか、
「こうすればいいんだよ」と教えていくと、比較的素直に聞くことができます。
気持ちを言葉にできると、 少し冷静になれるのです。
安心できる環境だから、自分の素の気持ちが出せるのです
ですからこういう子につきあうのは、少し忍耐が必要です。
ただこれは、決してあなたの育て方のせいではありません。
その子の持って生まれた性質なのです。
むしろ、安心できる環境だからこそ、自分の素の気持ちを出せる、
ということでもあります。子育てが基本的にはうまくいっている証拠です。
少し時間はかかりますが、成長するうちに、
逆に、優しさや豊かな感受性といった、その子の長所が発揮されて、
素晴らしいお子さんに育つに違いありません。
出典元:HSCの子育てハッピーアドバイス(一万年堂出版・2018) / 明橋大二著 / P.90~99引用
明橋大二先生、落ち着いてHSCとコミュニケーションを取るのですね

育てにくいと感じるHSCは、文句が多くて、
本人にしかわからない地雷があちこちにあるのですね。
起きるときは機嫌が悪く、寝るときも機嫌が悪かったり、
切りかえが苦手なため、かんしゃくを起こしては、親を手こずらせるこがあります。
芝居がかったようなことをするので、ひといちばい手がかかり、
ささいなことで深く気がつくのですね。
それを全て受け止めている親が、疲れてイライラしてしまうのは当然だと思います。
そんな敏感な性質をもった子どもと、どうやって接するのかというと、
表面的な行動だけに目を奪われずに、
「この子は、実は傷ついているのかもしれない」
と考えることが必要なのですね。
そして、そういう子にとって、自分をコントロールしてくれる
親の存在がとても大切なのですね。
ですから、まず親が少し落ち着くことが必要になります。
お互いにカッーっとなっている時は、
いったん離れて落ち着くのが一番よいのですね。
そして、親が少し落ち着いたら、子どもと向き合うことができるので、
まずは怒っていないことを伝えて、安心させることがいちばんです。
そして、ぎゅっと抱きしめて、子どもの気持ちに共感することが大切なのですね。
HSCは、もともと優しくて賢いので、冷静になればコミュニケーションを
うまくとることができるのですね。
ここまで読んで頂いてありがとうございました。
読んでくださった方の心がすこしでも元気になってもらえたら嬉しく思います。