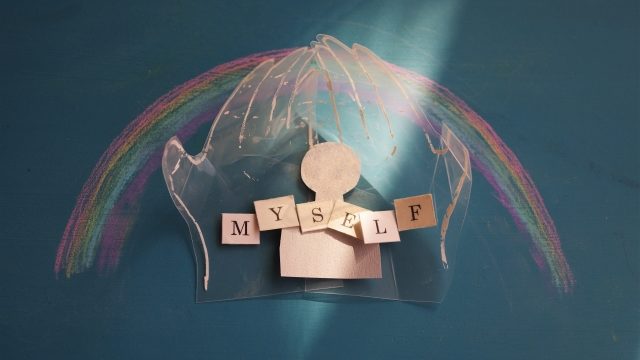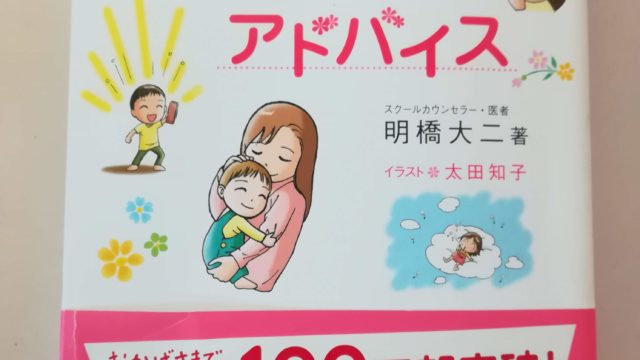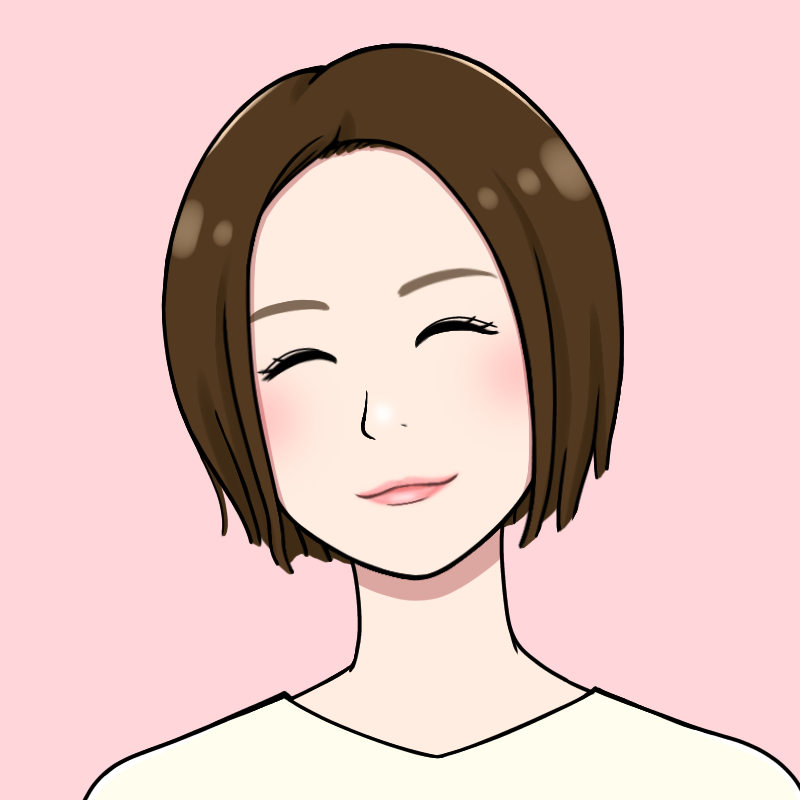子どもは泣くものと分かってはいても、
ちょっとしたことで泣くと、そんなことで?と驚いてしまいます。
それが続くと、うちの子こんなにすぐ泣いていて大丈夫かしら、
もっとつよい子になって欲しいのに、と心配になりますよね。
明橋大二先生の著書によると、
「泣く」ことで自分の気持ちが表現できるのはいいことで、
すぐに子どもが泣くのは、お母さんの育て方のせいではありません
とおっしゃっています。
でも、しょっちゅう泣いているとイライラしてしまうこともありますよね。
子どもが泣いたとき、どう対応すればいいのでしょうか。
明橋大二先生の著書「子育てハッピーアドバイス大好き!が伝わるほめ方・叱り方」より、
子どもが泣いたときにどうすればいいのかを、詳しく教えていただきましょう。
Contents
明橋大二先生はどんな人?明橋大二先生のプロフィール
明橋大二先生のことを初めて知った方もいらっしゃるかもしれませんので、明橋大二先生のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。
明橋 大二(あけはしだいじ)
昭和34年、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 子育てカウンセラー・心療内科医。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて、真生会富山病院心療内科部長。 児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。 専門は精神病理学、児童思春期精神医療。
著書は「なぜ生きる」(共著)、「輝ける子」、「思春期にがんばってる子」、「翼ひろげる子」、「この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ」、「10代からの子育てハッピーアドバイス」など多数。
明橋大二先生のおかげで子育てで大事なことが分かり、悩みが減って子育てが楽しくなりました。
明橋大二先生の著書より、子どもが泣いたら共感しましょう
「子どもは泣くもの」と思ってはいても、
あまりしょっちゅう泣かれると、お母さんもたいへんですね。
しかし、お母さんもわかっておられるとおり、
自分の気持ちを上手に言葉で表現できない子どもは、泣くことでしか伝えられません。
特に赤ちゃんなら、泣くのが唯一の表現手段です。
私は「泣く」という形で、きちんと自分の気持ちが表現できているのは、
むしろ、とてもいいことだと思います。
いちばん心配なのは、「泣く」という表現さえできず、
自分の気持ちを抑え込んでしまっている子です。
ですから、いわゆる「泣き虫」であったとしても、
心の発達上はそんなに心配ありません。
人一倍、感受性が豊かで、敏感な、優しい子なのかもしれません。
成長してから、りっぱな仕事を成し遂げた人が、
実は小さいとき、人一倍泣き虫だったというのは、よく聞く話です。
子どもがすぐに泣くのは、だから、お母さんの育て方のせいではないし、
子どもがおかしいのでもありません。
そこで、どう対応するかですが、
まず、泣いている子は、何かつらいことがあって泣いているわけですから、
怒ったらよけいに泣きたくなります。
それなのに、泣きやませようとして怒れば、さらに悪循環になってしまいます。
大切なのは、共感の言葉です。
「嫌だったんだね」「こうしたかんだね」と、子どもの気持ちを言葉にしてかけていく。
そして、よしよしと抱きしめてやります。
そのようにしてもらった子どもは、「親はわかってくれる」と、
周囲への信頼感を築いていきますし、気持ちを大切にしてもらったことで、
「自分は大切な人間なんだ」と、自己肯定感が育まれます。
それが土台となって、心の強い子が育つのです。
これは、どれだけしても、「甘やかし」にはなりません。
心配なのは、「泣いちゃダメ!」と子どもの感情表現を禁止して、
押さえ込んでしまう場合です。
もちろん、泣き声がつらくて言ってしまうこともありますが、あまりにもそれを続けると、
子どもは自分の気持ちを表現してはいけないんだ、と思ってしまいます。
すると、表面的には手がかからなくなりますが、
さまざまな感情を心の奥底にため込んでしまうので、
将来、思春期や青年期になったときにそれが爆発して、
よけいたいへんになることがあります。
また、もう1つ心配なのは、泣かれると困るからといって、
泣いたらすぐに子どもの要求にこたえてしまう場合です。
「抱っこして」など、体の具合が悪いときにこたえるのは問題ありませんが、
物の要求が通らないときに、すぐに買い与えてしまうのは、
「甘やかし」で、よくありません。
その両極端にさえならなければ、たいてい大丈夫だと思っています。
それでも、「どうしても泣き声を聞くとつらくなる」という人もあるかもしれません。
それは、お母さんがちょっと疲れているからか、あるいは、
もしかするとおかあさん自身が、泣きたい気持ちをガマンして、
がんばってきた人だからかもしれません。
自分が子どものころ、弟や妹が泣き虫で、
「でも私はお姉ちゃんだから泣いちゃいけない」と、がんばってきた。
それなのに、自分の母親はそんな気持ちに気づかず、
泣いている弟や妹の相手ばかりをしていた…。そういう背景があったりします。
泣くことは、子どもでも大人でも、決して悪いことではありません。
泣きたいときは、思いっきり泣いていいと思います。
それを誰かに受け止めてもらうことで、人はいやされ、
また前向きに生きていこうという意欲がわいてくるのだと思います 。
出典元:子育てハッピーアドバイス 大好き!が伝わるほめ方・叱り方(一万年堂出版・2010) / 明橋大二著 / P.186~189引用
明橋大二先生の著書を読んで、私も子どもも泣いていいと思えました

いかがでしたでしょうか。
泣ける子は、ちゃんと自分の気持ちを表現できているので大丈夫なのですね。
また、泣き虫なんじゃないかなと心配になる子も、
感受性が豊かで、敏感な、優しい子という、その子の個性なんですね。
むしろ心配なのは、泣いたときに「泣くな!」と言われ続けて、
感情を表現してはいけないと思って、感情を出せずに、
心の奥にため込んでしまうことなんですね。
ずっとずっとため込んでしまうと、いつか爆発してしまいます。
子どもも、大人だって泣いていいのですね。
気持ちをため込まず、思いっきり泣くことも必要なことですね。
そして、その気持ち共感にすることが、つよい心を育てる方法だと分かりました。
つよい心になれと、突き放すことでは心は育ちませんね。
気持ちを受け入れてもらうことで心は育つのですね。
子どもの気持ちを大切にして、心を育てていけるといいですよね。
ここまで読んで頂いてありがとうございました。
読んでくださった方の心がすこしでも元気になってもらえたら嬉しく思います。